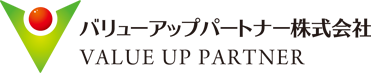FASでの経験は多様なキャリアに活きる
「その後、監査法人から財務アドバイザリーファームへ方向転換します。その背景と携わっていた業務内容を教えてください。」
1999年末にマザーズ市場が創設されたこともあり、早々に合格した会計士の友人・知人の中には、ベンチャーに転職してIPOを経験している人が増えました。ただ、私は合格が遅れたこともあり、上場を目指すベンチャー企業に転職するという話はありませんでした。そこで、次に何をしようかを考えた時に、登場し始めたばかりのFAS業務(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)を身につけておこうと思ったのです。そして、監査法人で6年弱勤めた後に、EY(EY TAS) に転職しました。Big4系のFAS会社は、一般に業務が縦割りになっていましたが、私は財務デューデリジェンス業務を中心に携わりました。
その中で、メガバンクによる証券会社の買収プロジェクトのプロジェクト・マネージャーを任せてもらったことが印象に残っています。そのプロジェクトでは、私がヘッドになって、お客様との予算組みから、EY TAS内の他のサービスライン(バリエーションチーム等)や税理士法人のアテンドなど、社内外の関係者を全て動かしていきました。ここで人や組織を動かす経験ができたことは今につながっていると思います。他に地銀の統合案件を2件並行してマネジメントしたこともありました。また、FAS業務では、監査法人時代より契約書に触れる機会が圧倒的に増えました。監査法人では年に1回程度(監査契約締結時)でしたが、FAS業務では案件ごとに契約書を随時確認します。自社とクライアントとの契約書だけでなく、M&Aの対象会社の契約書(株式譲渡契約書等)に触れる機会が多かったので大変勉強になりました。
「これからFASを目指す方にアドバイスはありますか?」
FAS業務の経験の後、どうなっていきたいかによると思います。ベンチャーのCFOであれば、何でもやらなくてはなりません。プロジェクトごとに、週単位や月単位で初めてチームを組む人をアサインして組織をマネジメントしたり、さまざまな契約書を確認したりする経験は役立つと思います。当時、大きなプロジェクトで数か月間にわたり毎日毎晩一緒に大変な思いをした人たちとは、今でもお付き合いが続いています。同じ釜の飯を食った人とは強固なネットワークができます。そうしたことも結果的に強みになっていると思います。もちろんテクニカル的な面でも成長できます。例えば、私自身の経験でお話すると、M&Aの後工程(PMI)の段階で、クライアントのメガバンクから依頼されて、監査法人が主張する会計処理を覆したことがありました。
その論点(組織再編関連)自体は、会計基準のどこにも書かれておらず、結果的に制度の穴となっていた論点でした。監査法人は、「この場合はこう処理する、次はこう処理する、それらをつなげるとこうなる」と既存の基準を継ぎはぎして、全体でみると、合理性に欠ける結果に行き着く会計処理の採用を主張していました。しかし、私は、どういう経路を辿ったとしても、最終的な結果は同一である必要があり、それが基準設定の趣旨にも合致すると主張し、最終的に監査法人の主張する会計処理を覆すことができたのです。これは、なかなか爽快なできごとでした。
「吉田さんは原理原則に則って考えているから、そういったことができるのでしょうね。」
そうですね。俯瞰する高い目線と、つぶさなことを見抜く間近な目線をうまく使い分けて、調整しながら物事を分析していくことは大切ですよね。

さまざまなハードルを超え、東証一部まで上場
「FASで6年弱勤務した後、43歳で初めての事業会社、それもベンチャーへとキャリアの大転換をした背景を教えてください。」
当時の会計士2次試験に合格したのが31歳なので、年齢に関してはあまり気にしていませんでした。ベンチャーへ転身したのは、実家が事業を営んでいたことも根っこにあったかもしれませんし、会計士の友人・知人たちがベンチャーでIPOを経験しているのを見てきたことも関係があったかもしれませんね。事業に関わりたいという思いはずっと持っていたように思います。そうした中で自分で何か商売をやるというよりは、粗削りな素材を加工していく方が自身には合っているのではないかという思いが、ベンチャーに転職した動機です。
「3年7か月後にマザーズに上場します。上場までの道のりをお聞かせください。」
入社して驚いたのは、私が入社することがごく一部の人にしか告げられておらず、「あなた誰?」という状況からスタートしたことです。また、「直前々期(N-2期)の半分まで来ている」と聞いて入社したのですが、実際には管理部門には社員一人しかいないという状態でした。そこからスタートして、1年間延期したものの3年7か月後にマザーズに上場しました。売上が10億円に満たない会社が、N証券で上場したことは珍しいと思います。財務会計面からみた場合、上場できた大きなポイントは2つあると考えています。1つは、ストック型のビジネスなので、しっかりと継続取引のストックを積み上げて収益の安定化を図っている点を評価してもらえたことです。そしてもう1つは、リース会計に「ノンキャンセブル」「フルペイアウト」という概念がありますが、この概念を取引契約上うまくチューニングすることで、ソフトウェアの販売時に、契約期間分の売上債権を、一気に確定することを可能としたことです。これは将来の営業キャッシュインフローを契約時点で確保することにもなり、資金面で非常に安定した経営を可能とすることにもなるので、この点も評価されたのだと思います。
「上場におけるハードルはありましたか?」
会社の中が整備されておらず、ITの会社なのに社内ネットワークの中も整理されていなくて、資料がどこに格納されているのかさえわからない状態から整理整頓していきました。また、管理部に対する意識が低く、経験値の高い人は雇えないので、まずは業務の一部を担ってくれる人を雇うところからはじめて、なんとか少人数でやりきったという感じでした。他にも、(これはよくある話ですが)予算と実績が合わないということがありました。N証券では、小さい会社だと月次決算に厳しく、常に上り調子で成長していかないとなかなか上場させてもらえません。それを実現したいのですが、現場がついてこられないという苦労はありました。ただ、運よく新しい製品発売のタイミングと重なり、収益が上がったことで何とか乗り切ることができました。
「その後、ほぼ最短で東証一部への市場変更を成し遂げます。簡単な道のりではなかったと思いますが、成功要因は何でしょうか。」
上場時の業績から当時の基準で最短での東証一部への市場変更が可能であったので、社長に確認をすると、「絶対に東証一部にいきたい」ということだったので、そのままN証券にお付き合いいただくことにしました。上場まで二人三脚で歩んできても、上場すると証券会社が離れてしまうのが通例です。それによって管理体制などが崩れてしまうことを懸念していたので、継続してお願いできたことは内部統制の維持の観点からも良かったと思います。
「東証一部への市場変更は、業績さえ整えば難しくなかったのでしょうか。」
上場してからは、資本提携等により事業成長を加速したいという意向もあり、拙速な判断でジョイントベンチャーを作り、うまくいかずに4か月で解消したこともありました。私の関与が、すでに基本契約を結ぶことになってしまっていた段階からであったので、本契約までの2週間の間で、何かあった時に会社を守れるような法的な縛りを顧問弁護士の先生にも協力頂きながら何とか契約に入れていきました。協業先は技術力のある企業でしたが、現場同士の十分な協議もないままに話が提携に向けて進んでしまった結果として、結局4か月という短期間で提携は解消となったのでした。しかし、そのことによって、株価が一定の基準値以下まで下落してしまうと東証一部に鞍替えはできませんので、新たにブロックチェーンの技術を展開する企業と早急に協業して、株価維持に努めたりもしました。その結果、時期や業績等含めいろいろな面でかなりギリギリでしたが、予定より2か月遅れで何とか東証一部にいかせてもらうことができました。市場変更を見据えている間は、ずっとどたばたの渦中にいるような感覚でした。
「次のキャリア選択の際も、ベンチャーに転職しますが、前職を退職した理由と、次も上場を目指すベンチャーを選択した理由をお聞かせください。」
東証一部まで上場してやりきった感覚を持っていました。また、自分の立場的に管理部門を担当しなくてはならないのですが、もう少しビジネス寄りの仕事にも足を踏み入れたいと思うようになっていました。そのために、もっと自由度が高く、今より能動的に動けるポジションで働きたいと考えていました。また、東証一部に市場変更した半年後に父親が病気になってしまって、入院先の病院を探したり、母親を病院へ送迎したりすることになりました。そこで、一区切りつけようと思い、会社を離れたという背景もありました。この時、家族との時間を優先したことは今でも母親に感謝されますし、少しは親孝行になったかなと思っています。その後、父親の病状が一時的に安定したので、ビジネス寄りの仕事ができる会社を探し、現在の株式会社ジオコードに転職しました。
「ビジネス寄りの仕事がしたいという話は、ジオコードへの入社前から社長に伝えたのでしょうか。」
そうですね。そこまで明確にではありませんが、やりたいことについては、お話はさせていただきました。