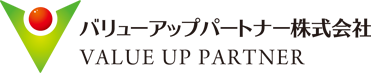転職の決め手は社長
「40歳の時に現職であるイントラストに転職します。現職の決め手を教えてください。」
転職を決めた理由は社長です。社長との面接の前にホームページを見ていると「お客様第一」と書かれていました。私は、そういう会社はたいてい営業が強く、裏を返せばバックオフィス系が弱いという印象を持っていました。極端な言い方をすれば、「経理は営業のためにやればいいんだ」と考えているくらいに思っていたのです。社長の桑原は営業出身でしたので、そういう勝手なイメージを持ちながら面接を受けました。
しかし、実際に話をしてみるとそのイメージは覆されました。「この社長ならば、経理・財務などバックオフィスの仕事についても真剣に向き合って話を聞いてくれるだろう。一緒に仕事ができそうだ」と感じたのです。そこで、入社することに決めました。
実際に、そのときの直感は間違っていませんでした。社長は、営業以外の仕事の分野に関しては、それぞれの話をよく聞いた上で、最終的な判断をくだしています。
また、前職は経理部長でしたので、もう少し上のポジションで仕事をしたいという思いも転職の決め手になりました。前職ではCFOの方がいらしたので、この会社でCFOを目指すのは現実的ではないと考えたのです。
「入社時は肩書がなかったようですが、その点はあまり気にならなかったのでしょうか。」
募集自体は、取締役候補者としてであったと記憶していますが、約束はなかったですし、私も肩書きを求めてはいなかったと思います。私が気にしたのは、上のポジションの方がいないということでした。イントラストは、自社の経理部門がない状態で、上には社長しかいなかったので、その点をクリアしていました。もし、上のポジションの方がいたら、違う選択をしていたかもしれません。あとは自分の実力次第だと思いました。
実際には、試用期間の定めがあるので、10月に入社し、1月1日に経理部長、4月1日に取締役になりました。
「どんな事業をされているのでしょうか。」
家賃債務保証がメインです。賃貸の物件を借りる際に、入居者が我々のような家賃保証会社に保証料を払い、我々が連帯保証人をお受けするというサービスです。入居者は連帯保証人を用意することなく入居でき、管理会社は滞納リスクを保証され、督促・回収業務から解放されるようになります。昔は、賃貸の物件を借りるときに、親や親戚に保証人になってもらっていましたが、現在はそうしたケースは少なくなっています。
さらに、家賃債務保証における審査、未入金時のご案内、裁判手続きなどのノウハウを生かして、医療費用保証、介護費用保証なども担っています。これらは、我々が作ったマーケットなので、一から創り上げている感覚を持っています。

最短スケジュールで上場したポイント
「入社後2年でマザーズに上場、その1年後には東証一部に市場変更しています。上場までの2年間はハードな日々だったと思いますが、上場を成功させるためにどんなことを大切にしながら行動していましたか。」
上場を目指して証券会社のキックオフミーティングをしたときに決めたスケジュールを2日前倒しで上場しました。証券会社の営業担当の方が、「自分の経験の中でも初めてだ」とおっしゃっていました。
スケジュール通りにできた理由は3つあると思います。
1つ目は、業績の安定性です。家賃債務保証はストックビジネスなので、業績がある程度安定していて、利益を出しやすい状況でした。
2つ目として、私が入社する前に事務を担当していた役員の方がきちんとやり切っていたということも挙げられます。
3つ目は、経営者の考え方です。社長は、「証券会社は上場についての専門家なので、彼らの言うことを聞くこと」という考えで、それを徹底していました。例えば、親会社と同じビルから移転したことも証券会社からのアドバイスでした。当時は親会社と同じビルにいたのですが、独立性の観点で、親子会社間の取引を解消していく方向に進めることになり、証券会社から「オフィスを分けた方がよい」と指摘されました。人によっては「親会社とオフィスが同じでも上場している会社はあるじゃないか」と言ったり、別の専門家から「ゴリ押しすれば大丈夫だよ」といった話を聞いたりすると、「移転しない」と判断する経営者もいると思います。しかし、うちの社長は、オフィスを移転する判断をしました。上場に関して一番詳しく、同じ方向を向いている専門家のアドバイスを第一に考えて行動したのです。専門家の言うこと素直に聞き、ひたすら解決していくという姿勢が鍵だったのだと思います。
「人の採用などもご担当されたのでしょうか。」
そうですね。経理については部署がなかったので、まず1人採用し、もう1人は社内から連れてきて、3人の体制でスタートしました。上場会社の子会社ということもあり、過年度修正などはなかったので、その点はやりやすかったです。
「親子上場で気を付ける点はありましたか。」
親子上場は、数値上の話で言うと、少数株主に利益が流れてしまうという懸念点があります。しかし、私はメリットもあると思っています。
上場会社の子会社という立場と、自社が上場している立場とは、全く違います。
例えば、予算作成についても、上場している会社は予算そのものも投資家の目も気にして作成しますし、常に成長を求められます。
それに対して、上場会社の子会社は、予算を達成することが第一目的となるので、おそらく保守的な予算を作って達成して終了となるケースが多いように思います。
子会社自身が上場していることで、自ら市場と向き合い成長を目指すことは、グループ全体の成長に寄与するという面はあると考えています。
社長と同じ方向を向いて失敗してみる
「既に現職で10年が過ぎようとしています。取締役CFOとして経営にあたる際に心掛けていることを教えてください。」
この会社に入ったときから「会社を潰さない」ということをモットーとしています。これができるのは社長とCFOだけなので、常に念頭にあります。
取締役CFOは責任があるポジションなので、発言にも影響力があります。数字を見て物事を判断するので、どうしても保守的になりがちです。「やる」という判断より「やらない」判断の方が、見た目の上でのリスクは少ないですからね。特に立場上、何かを始めるときにリスク面が頭をよぎるのです。
一方で、会社を成長させるためには挑戦が必要です。ですから、基本的に新しいものに対しては、門戸を開くことを意識しています。
「10年間の間、社長との信頼関係構築で気を付けている点を教えてください。」
ある会社のCFOが、社長との関係について「ダメだと思っても、一緒に失敗してみる」とおっしゃっていたことが印象に残っています。自分としては「これは苦しいな」と思っても、一緒に失敗してみることで信頼関係もできるし、チャレンジする経験を共にすることができるということでした。もちろん会社を潰さないということは大前提で。
その話を聞いた時は、「そうなんだ」と思った程度でしたが、何となく頭の中に残っていて、自分がCFOのポジションに就いたときには、しみじみ「確かにそうだな」と思ったのです。反対することも意見を言うことも大事ですが、まず、社長と一旦同じ方向を向いてみる。同じ方向を向いてうまくいけばそれにこしたことはないですし、軌道修正が必要になれば少しずつ修正していけばいいと思います。
「社長のビジネスパートナーとして、どのような関係性であるべきだと思いますか。」
同じ方向を向いて、励ましあうだけであれば、私である必要はないと思っています。それぞれの立場を自覚し、役割を果たした上で、関係性を作っていく必要があるでしょう。私はCFOなので、基本的には数字で判断し、数字で表現し、数字を提示しながら話すことが大切です。数字は客観的ですからね。